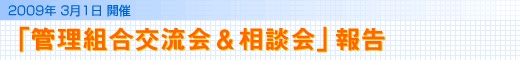
管理組合運営には様々な問題や悩みが発生します。
そこで管理組合の皆さんが、日頃どのような活動をされているのか情報を交換し、今後の組合運営の参考としてもらえるように交流会を開催しました。
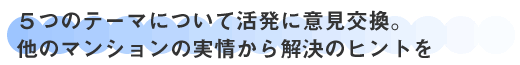
今回の参加者は43名。申し込み時に希望テーマをお伺いし、A.管理組合運営(滞納問題等)、B.管理組合運営(役員選任等)、C.管理組合運営(高齢者問題等)、D.修繕等、E. 住まい方(管理会社との関係等)の5つのテーマごとにテーブルを分け、各テーブル8人前後で話し合いを行いました。
各テーブルでは、活発な意見交換が行われ、休憩中や交流会終了後も、話がなかなか途切れないほどでした。話しあった内容を各テーブルの代表者が発表し、質疑応答が行われ、最後にコメンテーターに総括していただきました。
参加者のアンケートでは、「他のマンションの実情がよくわかり、自分のマンションと比較することができた」、「直面する問題の対応策について、よいアドバイスが受けられた」といった感想が寄せられました。
テーマA「管理組合運営(滞納問題等)」
- 管理会社との関係について
- 滞納問題について(滞納者への対応・総会での報告・未収金の回収方法など)
- 住民同士のコミュニケーションのとり方
- 総会への参加者を増やすには
まとめ
滞納問題については、滞納者といかに話し合いの接点をもつかに苦慮していることや、総会での報告の必要性、訴訟を行う場合の問題点や回収の可能性などについて、弁護士も交えて意見交換が行われた。
コミュニケーションについては、管理組合とは別に町会組織があり、2つの組織が連絡を取りながら活動している事例や、敷地内の草取りや広報紙の発行、修繕工事で対応しきれなかった部分の清掃活動等を通して、新しい入居者と管理組合、高齢者同士のコミュニケーションが図られている事例が報告された。
テーマB「管理組合運営(役員選任等)」
- 理事会の活性化について
- 名簿の作成について
- 管理会社との信頼関係について
- 大規模修繕と管理会社
- 役員選任の方法
- 管理組合法人について
- 長期修繕計画について
まとめ
理事(役員)のなり手不足の解決方法について。役員の選任については引継ぎのことを考えて3年交代にしている例が紹介された。
管理組合として情報をつかんでおくことの必要性があるが、住民名簿が個人情報の観点から作りづらくなっている状況が報告された。
長期修繕計画については国土交通省の長期修繕計画標準様式にあわせての見直しや、複数の修繕工事の周期をあわせることによりコストの削減、住民の中から建築士等の職業の人をブレーンに入れて組織をつくっていくことなどが話し合われた。
テーマC「管理組合運営(高齢者問題等)」
- 組合員の意識について
- 組合員の高齢化・無関心による理事のなり手の不足について
- 理事の役割、理事会活動の継続性について
- 管理会社との関係について
- 管理組合法人について
- その他(大規模修繕・耐震改修の実施、コミュニティ活動等)
まとめ
管理組合が抱える様々な問題について、1人で全てを解決していくことは困難であり、コミュニティ活動などを通して居住者間の横の繋がりを強く(仲間を増やす)して、管理組合全体で取り組んでいくことが重要。
管理会社に委託している場合であれば、管理会社の仕事を把握・確認すること。管理会社の業務の把握・確認ができているところは、管理会社の働きに満足している傾向がある。
テーマD「修繕等」
- コンサルの選定方法について
- 耐震診断結果に対するその後の方向性の検討
- エレベーターの保守管理について
まとめ
耐震診断をする際、耐震改修が必要との結果が出ても補修しづらいという問題や、既存不適格への対応などが話し合われた。
また、エレベーターの保守点検についてフルメンテナンス契約がよいのか、仕様の範囲内でメンテナンスを行い範囲外は別途費用が発生するPOG契約がよいのかについても意見交換がなされた。
テーマE「住まい方(管理会社との関係等)」
- 管理組合の理事の任期について
- 管理会社との付き合い方について
まとめ
同じ管理会社なのに一方ではとてもよく働いてくれる、一方では全然ダメということがある。これは管理会社の問題だけでなく管理組合の問題でもある。管理会社と対等につきあうには、理事がもっと勉強する必要がある。
管理会社の変更は慎重に進める必要があり、そのためには多くの情報を集めることが大切である。
コメンテーターまとめ
【弁護士】 役員や理事の頑張りをまわりがどうサポートするかも重要
管理組合の運営にあたっては、一人で悩まず色々な方と情報交換しながら進めていただきたいと思います。理屈の問題で法律論、制度論とは違う次元の話しとしてコミュニティをどうやって作るか、また、役員や理事の頑張りをまわりがどうサポートするかも重要だと思います。退職後、地域社会に戻ってこられた団塊の世代の方など、様々な社会経験(建築知識等)を持っていらっしゃる方が管理組合に入って、積極的に参加していただくのも良いやり方なのかなと思いました。
普段から管理費や修繕のことなどで議論されてまとまっている管理組合と、そうでない管理組合とでは、問題が起こったときの対応の仕方が全然違います。
マンションには、近所付き合いがわずらわしいからという理由で入居されている方が、戸建てに比べて多いのかもしれませんが、出来るだけ普段からコミュニケーションをとるように心掛けていただくことが重要だと思い ます。
【【建築士】 ベストな情報を判断して取り入れるのが、管理組合の役目
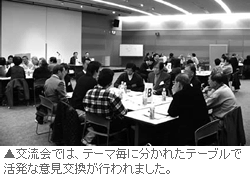 有効な情報がたくさんあって、その有効な情報を取り入れて、最終的には管理組合として何がベストかを暗中模索しながら判断していかなくてはなりません。常に前を見ながらも、時折これまでの歩みを振りかえり、確認しながら進めていくことが、マンション問題・マンション管理では必要ではないかと思います。
有効な情報がたくさんあって、その有効な情報を取り入れて、最終的には管理組合として何がベストかを暗中模索しながら判断していかなくてはなりません。常に前を見ながらも、時折これまでの歩みを振りかえり、確認しながら進めていくことが、マンション問題・マンション管理では必要ではないかと思います。マンション同士の交流という点では、マンション管理フェスタという催しもあるので、そういう中で個別の交流が深まり、それが広がっていったらいいなと思います。
<個別相談会> 2月22日(日)開催
専門家から貴重なアドバイス当日は専門家による個別相談会を実施。弁護士・建築士等の専門家から、9組(法律相談6組、管理一般相談1組、技術相談2組)の管理組合が問題解決のアドバイスを受けました。
相談内容は、管理費の未納、規則違反者への措置、ペット問題、管理人の時間外手当、修繕積立金見直しなどでした。

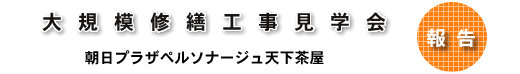
 総戸数108戸の朝日プラザペルソナージュ天下茶屋管理組合。まず理事長の金田さんから、自ら作成された資料「大規模修繕工事の計画と実行」をもとに説明がありました。
総戸数108戸の朝日プラザペルソナージュ天下茶屋管理組合。まず理事長の金田さんから、自ら作成された資料「大規模修繕工事の計画と実行」をもとに説明がありました。 今回の工事は、修繕にとどまらず、エントランスホール、管理事務所などの共用部分を中心に、より明るく安全性を高めるための改良工事にも力を入れている点も大きな特徴です。つねに透明性と公平性を確保しつつ計画を進めてきた金田理事長の説明を聞きながら、充分な修繕積立金や、綿密かつ入念な計画と実行ぶりに会場からは感心のため息が何度も漏れていました。その後の質疑応答では、修繕積立金の見直しをしたきっかけ、管理会社と大規模修繕との関係、長期修繕計画などについての質問がありました。
今回の工事は、修繕にとどまらず、エントランスホール、管理事務所などの共用部分を中心に、より明るく安全性を高めるための改良工事にも力を入れている点も大きな特徴です。つねに透明性と公平性を確保しつつ計画を進めてきた金田理事長の説明を聞きながら、充分な修繕積立金や、綿密かつ入念な計画と実行ぶりに会場からは感心のため息が何度も漏れていました。その後の質疑応答では、修繕積立金の見直しをしたきっかけ、管理会社と大規模修繕との関係、長期修繕計画などについての質問がありました。 続いて施工会社から、現在行われている躯体修繕工事、シーリングの打ち替え工事などの模様を映像を使って、一つずつ丁寧に説明していただきました。動画なのでわかりやすく、参加者の方々も興味深そうにご覧になっておられました。
続いて施工会社から、現在行われている躯体修繕工事、シーリングの打ち替え工事などの模様を映像を使って、一つずつ丁寧に説明していただきました。動画なのでわかりやすく、参加者の方々も興味深そうにご覧になっておられました。 そして、いよいよ現場見学。3班に分かれて、金田理事長、施工会社、監理事務所の案内で現場を周りました。塗装の過程や、補修の実演、タイルの補修の様子など説明を聞きながら熱心に見学。現場見学の後は、再び質疑応答です。施工会社の公募方法や、施工会社を選んだ決め手など、参加者からは熱のこもった質問がいくつもなされ、大規模修繕工事への関心の高さを改めて実感。そして予定の時間をオーバーする形で、無事終了しました。ご協力いただいた朝日プラザペルソナージュ天下茶屋管理組合の方々、および関係者の方々に心よりお礼を申し上げます。
そして、いよいよ現場見学。3班に分かれて、金田理事長、施工会社、監理事務所の案内で現場を周りました。塗装の過程や、補修の実演、タイルの補修の様子など説明を聞きながら熱心に見学。現場見学の後は、再び質疑応答です。施工会社の公募方法や、施工会社を選んだ決め手など、参加者からは熱のこもった質問がいくつもなされ、大規模修繕工事への関心の高さを改めて実感。そして予定の時間をオーバーする形で、無事終了しました。ご協力いただいた朝日プラザペルソナージュ天下茶屋管理組合の方々、および関係者の方々に心よりお礼を申し上げます。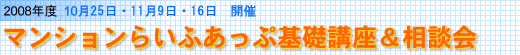
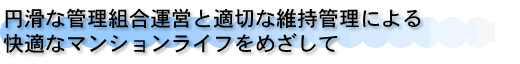

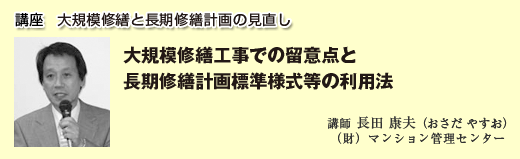
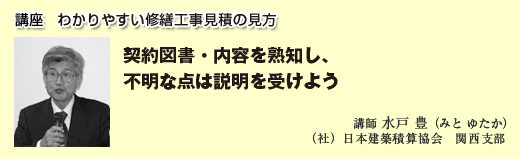
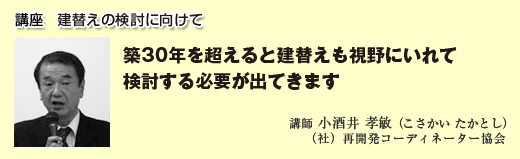
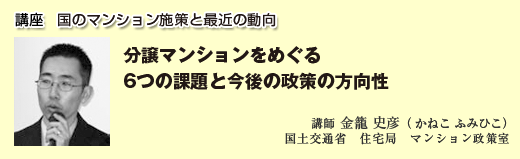
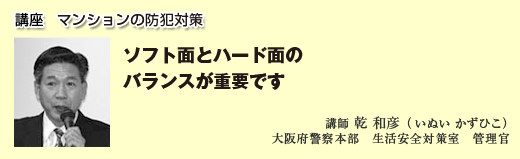
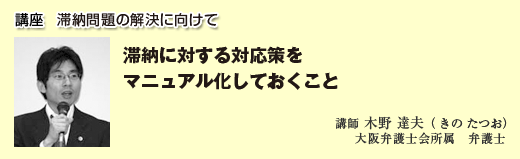
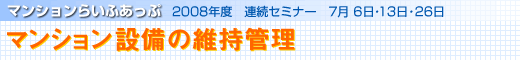

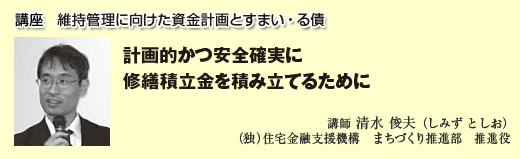
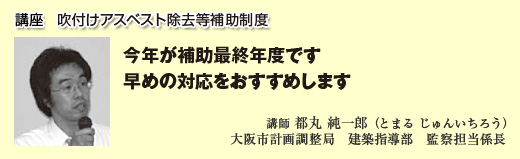
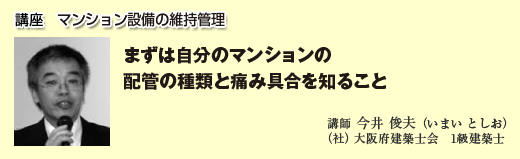
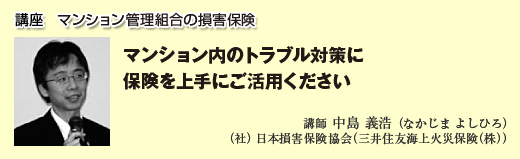
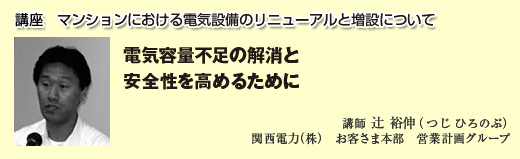
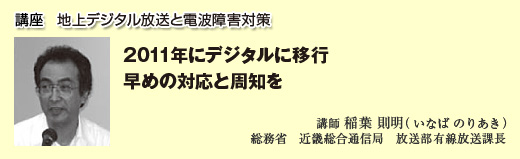
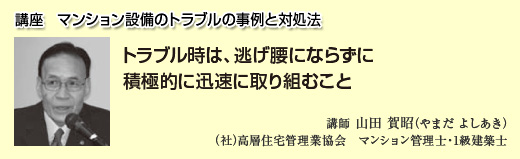
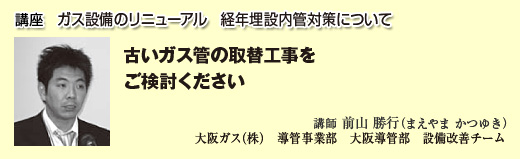
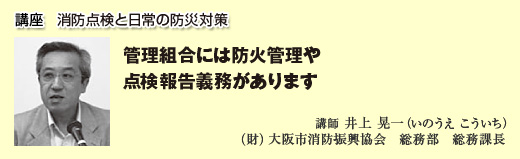

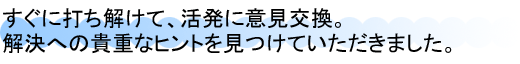
 例えば、自分のマンションの屋上に上がったことがあり ますか?屋上のドレンにごみがあれば、管理組合は管理 会社に清掃を指示しなければいけません。しかし屋上 に上がらなければ、それはできません。まずマンション の状態を知ること。そこから対応を考えてください。
例えば、自分のマンションの屋上に上がったことがあり ますか?屋上のドレンにごみがあれば、管理組合は管理 会社に清掃を指示しなければいけません。しかし屋上 に上がらなければ、それはできません。まずマンション の状態を知ること。そこから対応を考えてください。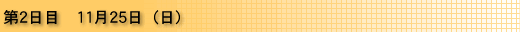
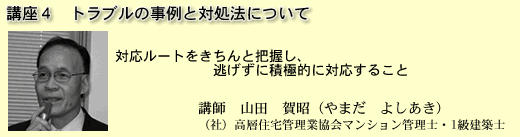
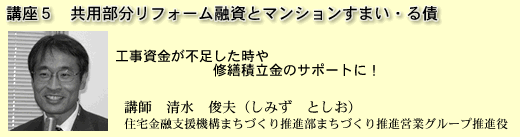
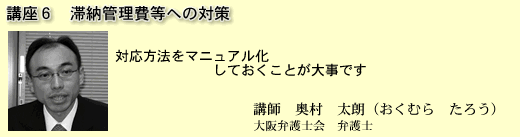

 総戸数1016戸を誇る京橋グリーンハイツ管理組合。まず理事長の市川さんから、今回の工事見学会申し入れに対し理事会が歓迎の気持ちを込めて決議したこと、そして2回目の大規模修繕工事が、昨年秋の業者選定等の準備から始まって、来年3月に終了する足かけ3年の長期工事であること。工事方式は、設計監理会社を採用せずに、居住者が工事を自ら監督する施工業者の責任施工方式を採ったことなどに触れた上で、大規模修繕委員会設立までの経緯の説明がありました。
総戸数1016戸を誇る京橋グリーンハイツ管理組合。まず理事長の市川さんから、今回の工事見学会申し入れに対し理事会が歓迎の気持ちを込めて決議したこと、そして2回目の大規模修繕工事が、昨年秋の業者選定等の準備から始まって、来年3月に終了する足かけ3年の長期工事であること。工事方式は、設計監理会社を採用せずに、居住者が工事を自ら監督する施工業者の責任施工方式を採ったことなどに触れた上で、大規模修繕委員会設立までの経緯の説明がありました。 通常の大規模修繕工事の他に、足場がある時にしかできない改善・改良工事を行ったこと、現状のままでは資金不足が生じるため、アンケート実施のうえで修繕積立金を値上げしたこと、外装の建物診断を行ったこと、他にも、施工業者選定には、統一見積書を作成したことや、金額が安いところではなくて、工事の実績やクレームのないところの他にISOをベースにした施工管理ができるところなどを重視したそうです。「工事仕様書に、検査・品質保証の項目を入れると、施工業者さんも気をつけられると思いますよ」とアドバイス。参加者の皆さんも興味津々の様子でした。
通常の大規模修繕工事の他に、足場がある時にしかできない改善・改良工事を行ったこと、現状のままでは資金不足が生じるため、アンケート実施のうえで修繕積立金を値上げしたこと、外装の建物診断を行ったこと、他にも、施工業者選定には、統一見積書を作成したことや、金額が安いところではなくて、工事の実績やクレームのないところの他にISOをベースにした施工管理ができるところなどを重視したそうです。「工事仕様書に、検査・品質保証の項目を入れると、施工業者さんも気をつけられると思いますよ」とアドバイス。参加者の皆さんも興味津々の様子でした。 質疑応答では、工事仕様書作成にかかった期間と人数、バルコニーの室外機以外の物の取扱、専門委員の報酬の有無、義務を果たさない居住者への対応方法、ゴンドラ使用の長所短所、建物診断の費用など、多くの質問がありました。
質疑応答では、工事仕様書作成にかかった期間と人数、バルコニーの室外機以外の物の取扱、専門委員の報酬の有無、義務を果たさない居住者への対応方法、ゴンドラ使用の長所短所、建物診断の費用など、多くの質問がありました。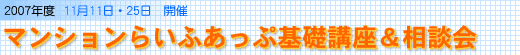

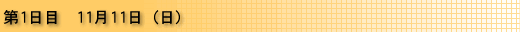
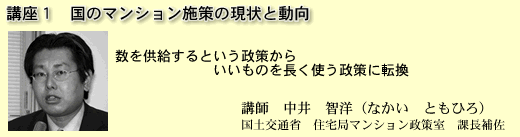
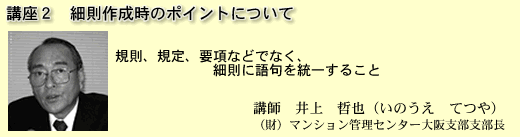
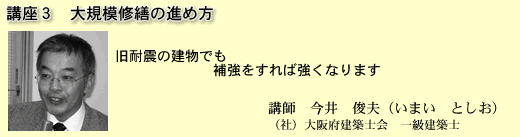
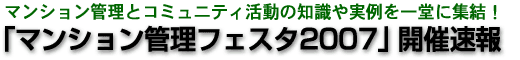
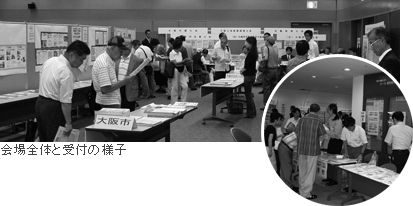

 マンション学をテーマに研究されている藤本佳子教授(千里金蘭大学)がミニ講演としてコミュニティづくりの大切さを講演された後、大阪市内の3つのマンションの管理組合(エバーグリーン淀川、勝山東ガーデンハイツ、ベイシティ大阪)のコミュニティ活動を紹介。マンション管理組合活動の参考にしてもらいました。
マンション学をテーマに研究されている藤本佳子教授(千里金蘭大学)がミニ講演としてコミュニティづくりの大切さを講演された後、大阪市内の3つのマンションの管理組合(エバーグリーン淀川、勝山東ガーデンハイツ、ベイシティ大阪)のコミュニティ活動を紹介。マンション管理組合活動の参考にしてもらいました。 大阪市マンション管理支援機構の専門家6団体(大阪弁護士会、大阪司法書士会、大阪土地家屋調査士会、(社)大阪府不動産鑑定士協会、近畿税理士会、(社)大阪府建築士会)の専門家と自由におしゃべりできるコーナーを設置。当日は、多くの方が熱心に相談される姿が目立ちました。相談内容は、管理運営の問題、管理会社とのつきあい方、修繕によるトラブルなど実に様々でした。
大阪市マンション管理支援機構の専門家6団体(大阪弁護士会、大阪司法書士会、大阪土地家屋調査士会、(社)大阪府不動産鑑定士協会、近畿税理士会、(社)大阪府建築士会)の専門家と自由におしゃべりできるコーナーを設置。当日は、多くの方が熱心に相談される姿が目立ちました。相談内容は、管理運営の問題、管理会社とのつきあい方、修繕によるトラブルなど実に様々でした。


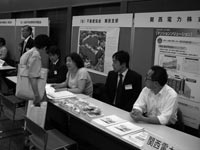 大阪市、大阪市住まい公社、(独)住宅金融支援機構 近畿支店から、住まいに関すること、関連資金のことなどの役立つ情報を提供。さらに、大阪ガス(株)、(社)不動産協会、(社)宅地建物取引業協会、関西電力(株)など大阪市マンション管理支援機構の賛助団体の活動を紹介。(社)高層住宅管理業協会は相談をお受けしました。
大阪市、大阪市住まい公社、(独)住宅金融支援機構 近畿支店から、住まいに関すること、関連資金のことなどの役立つ情報を提供。さらに、大阪ガス(株)、(社)不動産協会、(社)宅地建物取引業協会、関西電力(株)など大阪市マンション管理支援機構の賛助団体の活動を紹介。(社)高層住宅管理業協会は相談をお受けしました。


 大規模修繕工事・建替え事例・超高層住宅など、マンションに関する様々なビデオをご覧いただきました。
大規模修繕工事・建替え事例・超高層住宅など、マンションに関する様々なビデオをご覧いただきました。 さる9月2日に開催された「マンション管理フェスタ2007」の全体の模様は前号(22号)でご紹介しましたが、誌面の都合で掲載できなかった講演「マンション管理とコミュニティ活動」の内容を後編としてご紹介します。
さる9月2日に開催された「マンション管理フェスタ2007」の全体の模様は前号(22号)でご紹介しましたが、誌面の都合で掲載できなかった講演「マンション管理とコミュニティ活動」の内容を後編としてご紹介します。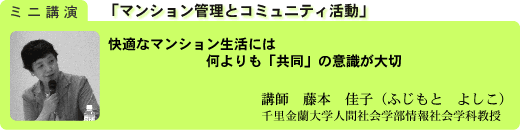
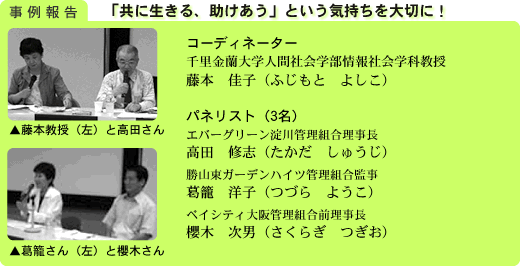
 藤本●コミュニティ形成に成功した例をご紹介ください。
藤本●コミュニティ形成に成功した例をご紹介ください。 藤本●葛籠さんのところでは、大規模修繕の時に「マンション元気村」という修繕ニュースを出されましたが、それはどんな役割を果たしましたか。
藤本●葛籠さんのところでは、大規模修繕の時に「マンション元気村」という修繕ニュースを出されましたが、それはどんな役割を果たしましたか。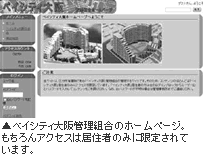 櫻木●私どもではコミュニティ形成のために昨年ホームページを開設しました。理事会の議事、ペットクラブの活動や、子供会の活動などを写真を取り入れながらお知らせなどに使っています。また意見ももらえるシステムになっていますが、活用の状況を1年間見ますとまだ不十分です。
櫻木●私どもではコミュニティ形成のために昨年ホームページを開設しました。理事会の議事、ペットクラブの活動や、子供会の活動などを写真を取り入れながらお知らせなどに使っています。また意見ももらえるシステムになっていますが、活用の状況を1年間見ますとまだ不十分です。