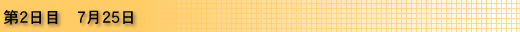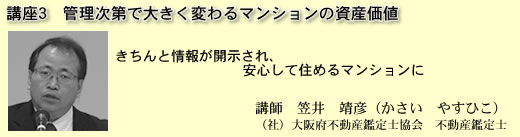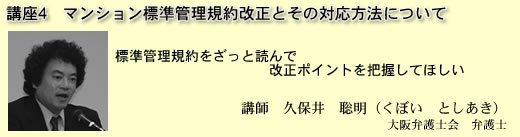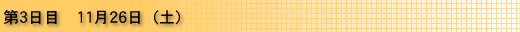
管理組合会計の役割と特徴や、快適住環境推進運動の展開事例、そして全員参加型のクイズ形式によるマンション管理Q&Aなどをテーマに開催しました。
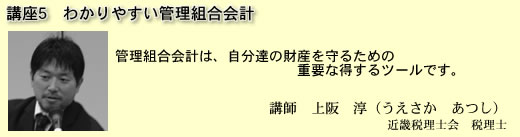
管理組合会計がどうも分からないという方もいらっしゃると思いますので、管理組合会計の根本的な考え方をご紹介します。そもそも管理組合の収入源は、原則的に入居者の方から徴収された管理費であり、それを1年間どうやって運営するのかを考えるのが理事会です。その運営に基づいて支出した分が、予算に比べてどうかを考え、それが適正かどうかを明示していくのが会計担当の方の役目です。さらにそれが最終的に正しいかどうかチェックするのが監事の役割です。管理組合会計の原則は、共用部分の維持管理をしながら、管理費の収入をロスなく使い、次の方にバトンタッチしていく。たくさんお金があるからバンバン使っていいというわけではなく、将来のことも考える責務もあります。
会計の世界では全体損益計算と期間損益計算という考え方があります。全体損益計算は、会社であれば、設立から会社が倒産・廃業、解散するまでということになりますが、これでは、現在はどうなのかがわかりませんので、一定の期間で区切るのが、期間損益計算です。管理組合の場合でも月次の収支計算書で確認をし、1年間が終わったときに収支計算書の金額と予算とを対比する流れになります。例えば1年間が終わり、はっと気が付くと水道光熱費が予算オーバーということがあります。もし月次で管理していたら、途中の段階で気がついて、どこかに漏れがあるのか、読みが甘かったのか、ということがわかります。
新聞などを見ていたら、某銀行で十数億の横領とかが起きる。それはチェック体制が甘いからです。一定のルールがない。継続性がない。明瞭性がない。誰が見てわかるように、要求されたときに今の実態がある一定の法則に基づいて同じ結果になるという状況を確保していないからです。
会計は、数字を羅列して、ただ単に事後のことを帳簿につけることが目的ではなく、事後の帳簿、もしくはその事実に基づいて、将来どうしていくのかを見ていくことが重要です。だから継続性を無視したり、いい加減にするような方が役職についた時に困るし、もしやり方等がわからなければ分かる方に聞くなどして、正確性を高めていく努力をされないと、結局はご自身も含めて皆さんが困るようなことになります。
管理組合会計は、できるだけ皆さんが拠出されたお金を無駄に使わないようにお互いが、いい意味の干渉をし合って、将来の自分達の財産を守るように使うための重要な得をするツールだと思っていた
だき、管理組合会計にもう少し目を向けていただけたらと思います。
 挨拶運動、講習会、防犯パトロールなど多彩に実施
挨拶運動、講習会、防犯パトロールなど多彩に実施講師 高田 修志(たかだしゅうじ)
エバーグリーン淀川地上館 管理組合 理事長
当管理組合(自治会協力)では、より快適な住環境を求めて住民全員参画により「快適住環境推進運動」に取り組みました。その内容は次の通りです。
- 「管理規約」に「コミュニティの形成と育成」の条文を追加し、意識付けをしました。
- 全住民対象に「快適住環境推進」の標語募集し、作品をエレベーターホールに掲出しました。
- 行動形態としては「挨拶運動」から入り、期間中理事・代議員、管理事務所職員よるデモンストレーションを行いました。日がたつに従って通学する小学生・中学生から自発的に「おはようございます」と声が出るようになりました。
- 住民のためのコミュニティサルーン(談話室・寛ぎの間)をあまり使われていない集会室を改装してオープンしました。
- この期間に定例となっている「防犯講習会」「救急救命研修会」の他に「健康管理講習会」を医誠会病院の先生にお願いしました。(好評)
- 「快適住環境」に対する論文(提言)を募集し、発表しました。
- 「防犯パトロール」も防犯協議会のメンバーで続けています。
- 迷惑行為排除のための「べからず集(28項目10項)」を手作り作成し、全戸に配り徹底を図り、毎月実行課題を設け促進することにしました。
- 各クラブ活動(老人会・踊りの会・卓球・テニス・少年野球・ペット飼育者連絡協議会)等の活性化。
- 構内の整理・整頓、タバコのポイ捨て、犬の糞の片付等の清潔感の醸成。やはり結果を出すためには“継続は力なり”で根気よく続けたいと肝に銘じています。
←前へ 次へ→

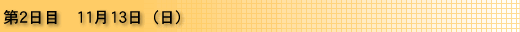
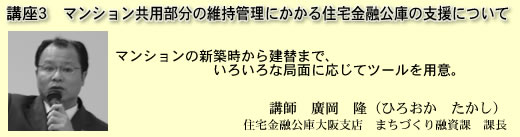
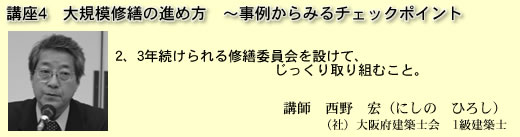
 停電や火災を防ぐには電気配線の改修が必要です
停電や火災を防ぐには電気配線の改修が必要です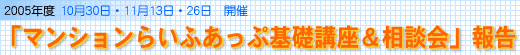

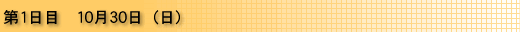
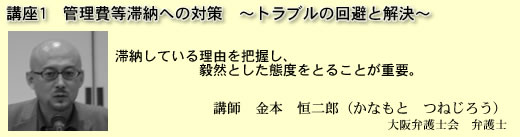
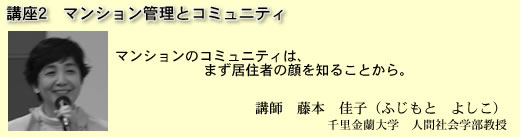
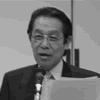 契約の更新時に、重要事項説明が必要となりました
契約の更新時に、重要事項説明が必要となりました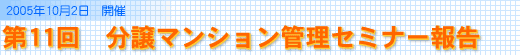 管理会社に不満を抱き、両者の関係がぎくしゃくしている管理組合が少なくありません。そこでもっと管理会社と上手とつきあっていくための考え方を、社団法人高層住宅管理業協会の入村理事に講演していただきました。
管理会社に不満を抱き、両者の関係がぎくしゃくしている管理組合が少なくありません。そこでもっと管理会社と上手とつきあっていくための考え方を、社団法人高層住宅管理業協会の入村理事に講演していただきました。 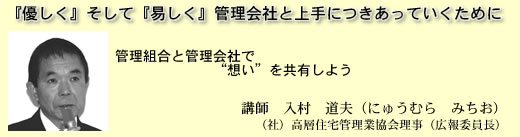



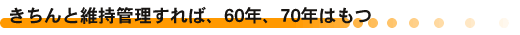
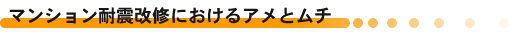
 一方、規制強化という観点でみると、耐震改修促進法では、個人住宅とマンションは勝手にやりなさいとばかりに、対象から実質的に除外されている。しかし公的な関わりが強まっているマンションで、本当にこれでいいのか。車には車検制度があります。車検をうけなければ車を維持することができません。住宅にはそういうものがないわけです。住む以上は、一定の性能をもっていなければ住めないような形が、本来あるべきだと思います。売買時には、そういった検査制度もいるのではないか。ですからアメとムチの対策が、うまく揃っていけば、マンションの耐震改修をしていくうえで、非常に有効でないかと私は考えております。
一方、規制強化という観点でみると、耐震改修促進法では、個人住宅とマンションは勝手にやりなさいとばかりに、対象から実質的に除外されている。しかし公的な関わりが強まっているマンションで、本当にこれでいいのか。車には車検制度があります。車検をうけなければ車を維持することができません。住宅にはそういうものがないわけです。住む以上は、一定の性能をもっていなければ住めないような形が、本来あるべきだと思います。売買時には、そういった検査制度もいるのではないか。ですからアメとムチの対策が、うまく揃っていけば、マンションの耐震改修をしていくうえで、非常に有効でないかと私は考えております。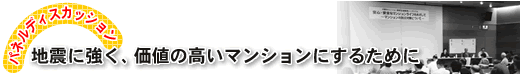
 [コーディネーター]
[コーディネーター] [パネリスト]
[パネリスト] [パネリスト]
[パネリスト] [パネリスト]
[パネリスト] 私自身は、「地震保険の活用推進」がひとつのポイントになるかと思います。といいますのは、住宅ローン融資の減税はあまり実効性がない。そこで地震保険(の掛け金)をもう少し安くしようというのが今回の提言です。地震保険にマンションの皆さんが入っていただきますと、例えば耐震改修をすると割引される。そうなると、保険金を割り引くために改修しよう、という話がしやすくなるんじゃないかなと思います。
私自身は、「地震保険の活用推進」がひとつのポイントになるかと思います。といいますのは、住宅ローン融資の減税はあまり実効性がない。そこで地震保険(の掛け金)をもう少し安くしようというのが今回の提言です。地震保険にマンションの皆さんが入っていただきますと、例えば耐震改修をすると割引される。そうなると、保険金を割り引くために改修しよう、という話がしやすくなるんじゃないかなと思います。 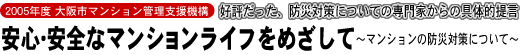
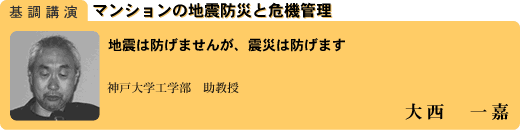
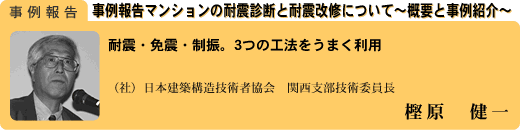
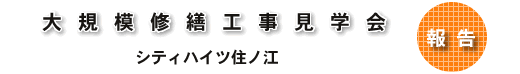
 1回目の大規模修繕は、管理会社の設計施工方式で実施しましたが、数年前から入居者の間で、歩こう会やクラシックなど趣味を同じくする者が集まったコミュニケーション組織ができ、大規模修繕についても、自分達の住まいをもっと良くしたい、納得のいく大規模修繕を行いたいという声が自然にわきおこり大規模改修委員会が組織されました。大規模改修委員会は、管理組合での歴代の施設担当委員や、建設関係の仕事に携わる人などを含めて構成されました。大規模改修委員会は、パートナー(専門家)である建物調査会社を選定し、調査・設計業務を委託しました。施工業者については、マンションの掲示板・ホームページ・マンション専門紙により公募し、見積りの比較検討、業者へのヒアリングを行い決定しました。
1回目の大規模修繕は、管理会社の設計施工方式で実施しましたが、数年前から入居者の間で、歩こう会やクラシックなど趣味を同じくする者が集まったコミュニケーション組織ができ、大規模修繕についても、自分達の住まいをもっと良くしたい、納得のいく大規模修繕を行いたいという声が自然にわきおこり大規模改修委員会が組織されました。大規模改修委員会は、管理組合での歴代の施設担当委員や、建設関係の仕事に携わる人などを含めて構成されました。大規模改修委員会は、パートナー(専門家)である建物調査会社を選定し、調査・設計業務を委託しました。施工業者については、マンションの掲示板・ホームページ・マンション専門紙により公募し、見積りの比較検討、業者へのヒアリングを行い決定しました。 続いて、改修委員会のメンバーから体験談として、大規模修繕工事を成功させるポイントをお聞きしました。改修委員会のメンバーの選定について、リーダーは自分の考えを押し付けるような人ではなく、メンバー間の意見の食い違いをうまくまとめる能力が必要であること、メンバーに建設関係の区分所有者が入ると利害関係が発生する場合があることなど紹介されました。また、管理組合の立場にたったパートナー(専門家)を選定することが重要で、予算上の問題もあるが業務委託費用の安さだけを選定基準にすべきではないというお話などもあり、これから大規模修繕工事に取り組む管理組合にとって、たいへん参考になるポイントがいくつも紹介されました。
続いて、改修委員会のメンバーから体験談として、大規模修繕工事を成功させるポイントをお聞きしました。改修委員会のメンバーの選定について、リーダーは自分の考えを押し付けるような人ではなく、メンバー間の意見の食い違いをうまくまとめる能力が必要であること、メンバーに建設関係の区分所有者が入ると利害関係が発生する場合があることなど紹介されました。また、管理組合の立場にたったパートナー(専門家)を選定することが重要で、予算上の問題もあるが業務委託費用の安さだけを選定基準にすべきではないというお話などもあり、これから大規模修繕工事に取り組む管理組合にとって、たいへん参考になるポイントがいくつも紹介されました。
 工事概要については、施工会社から、仮設計画から各工事工程での作業内容や検査体制まで分かりやすく説明していただきました。
工事概要については、施工会社から、仮設計画から各工事工程での作業内容や検査体制まで分かりやすく説明していただきました。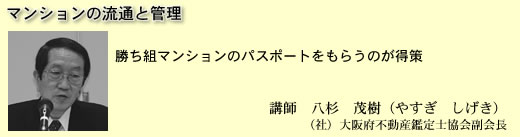
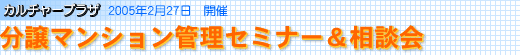
 セミナーでは、(社)日本建築家協会・メンテナンス部会の星川晃二郎元部会長に、マンションを良好に維持管理するための大規模修繕の進め方のポイントと、改修によるグレードアップの事例紹介を、(社)大阪府不動産鑑定士協会の八杉茂樹副会長に、マンションの資産価値を高める管理の重要性について、分かりやすく解説していただきました。
セミナーでは、(社)日本建築家協会・メンテナンス部会の星川晃二郎元部会長に、マンションを良好に維持管理するための大規模修繕の進め方のポイントと、改修によるグレードアップの事例紹介を、(社)大阪府不動産鑑定士協会の八杉茂樹副会長に、マンションの資産価値を高める管理の重要性について、分かりやすく解説していただきました。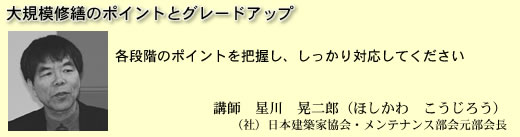
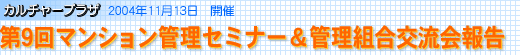
 セミナーでは、財団法人マンション管理センターに寄せられた相談事例の中から、とくに多い相談内容の上位5項目を中心に、財団法人マンション管理センター大阪支部・宇都宮忠支部長に講演していただきました。
セミナーでは、財団法人マンション管理センターに寄せられた相談事例の中から、とくに多い相談内容の上位5項目を中心に、財団法人マンション管理センター大阪支部・宇都宮忠支部長に講演していただきました。 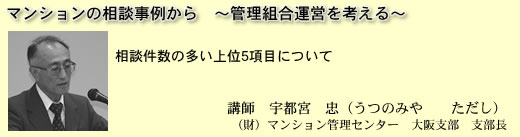



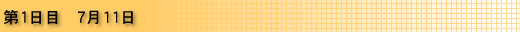
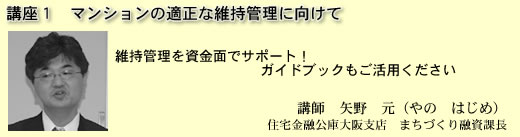
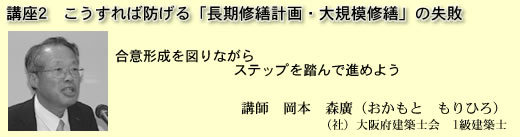
 ミニ講座1 共用部変更をともなう給湯設備改善による快適性の向上
ミニ講座1 共用部変更をともなう給湯設備改善による快適性の向上