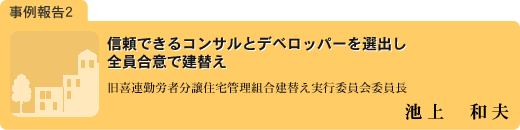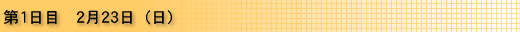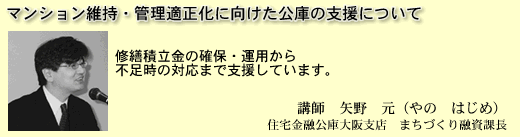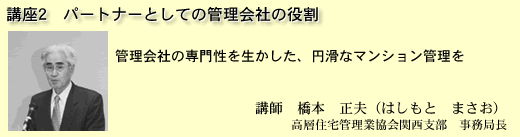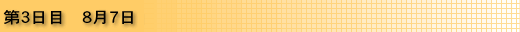
マンション会計における適正な会計管理とペイオフ対策などをテーマに開催しました。
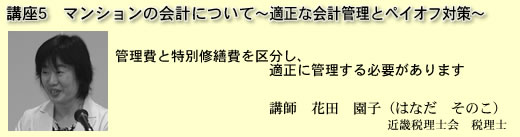
マンションの管理組合は、年に1度の定期総会で、事業報告と決算報告ですね、それと次期事業計画と予算を承認してもらわなければなりません。そのためには、事業報告、事業計画とともに、決算書の作成が必要になってきます。決算書の作成は、多くの管理組合では、管理会社の方がしてくれると思うのですが、自主管理の組合ですと、自分たちで作っていかねばなりません。そこで会計担当理事になるのは、会社で経理をやっている方が多いため、一般的な企業の会計を使うことが多いようなんですね。また、管理組合の会計基準というのが定めがありません。ですので管理会社の方でもさまざまな様式で作成されていまして、問題点も出てきております。
マンションの管理組合会計については、マンションの管理の適正化に関する指針が出ているのですが、公益法人であるとか、NPO法人であるとかは、法律で会計基準が決まっていますが、管理組合の会計にはそういう決まりがありません。単に管理費と特別修繕費を明確に区分経理して、適正に管理する必要がありますよ、ということが言われています。
また、管理組合会計の特長としまして、企業会計は利益を出すことを目的として会計を行っているのですけど、組合会計は、共用部分の維持管理を適切に実施するために、予算と実績を適正に管理していくというのが目的です。ですから修繕費をけちって、きちんと維持できなかった、管理できなかったというのは、ちょっと問題です。そのために、予算を決めて、予算準拠主義で会計をやっていきます。あと、大規模修繕工事に備えて修繕積立金会計を区分して管理していく。これが一番大事ですよね。すごいお金がかかりますので、それに備えてちゃんと毎月、積立金会計を区分して管理していかなければなりません。
ペイオフ対策なんですけど、一金融機関、一預金者あたりということになっていますので、まず分散ですよね。国内の都銀すべてに1行ずつ1000万ずつ預けるとか。あとは都銀と地銀と信金と郵貯と、それぞれに1000万ずつ預けるとかですね。
あと、つぶれない金融機関の選択なんですけど、大きいから安全とは言い切れません。予想できませんので、ニュースや経済新聞、あるいはディスクロージャー誌をチェックされたり、格付け評価機関の評価だとか、株価などを参考にされたらどうでしょうか。
日商岩井阿波座マンション管理組合 理事長
安全、安心、快適性を求めて管理組合として取り組んできた事例を平成12年から時系列的に主なものをご紹介します。
平成12年にゴミステーションを使わなくなりましたので、管理組合の倉庫、備品だとか書類などを入れる倉庫にし、残った分を自転車、バイク置き場としました。
平成13年に、次に防犯対策ということで、ピッキングに強いディンプルキーに替えるように推奨致し、監視カメラも各要所に取り付けました。また、給水システムにおいて、受水槽、高架水槽を撤去し、増圧直結給水方式のポンプに切り替えました。多少お金がかかりましたが、新鮮な水道が供給できました。なおかつ、受水槽室を改造して、集会室に有効利用しました。
平成14年には、玄関アプローチで、通路と玄関テラスが2段の階段と、一部が狭く傾斜のきついスロープだったのを、防滑を兼ねたインターロッキングで段差をなくして、緩斜面のバリアフリー通路に改造致しました。
また、ここのマンションは、もともとペットが禁止されていたんですけど、飼っていた方がおられます。そうかといってあまり表立って言いますと角が立ちますので、平成15年に、ペット禁止のステッカーを掲示しました。そして平成16年には設計図面のCD化を行いました。
管理組合運営のポイントは、管理会社任せにしないことや、専門家を活用することだと思います。 ※(注)講座1〜5&ミニ講座1〜3の講師の役職、部署等は講演時のものです。
←前へ

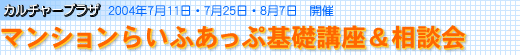
 快適で安心なマンション生活を送るには、適正にマンションの維持管理を行う必要があります。その維持管理の主人公は、居住者であり、管理組合です。
快適で安心なマンション生活を送るには、適正にマンションの維持管理を行う必要があります。その維持管理の主人公は、居住者であり、管理組合です。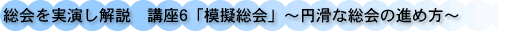
 ■伊藤 寛
■伊藤 寛  ■花田 園子
■花田 園子  ■北田 五十一
■北田 五十一 

 交流会の最後に、全体の前で、グループ毎でどのような話がされて、どのように感じたか、参考になったこと等、発表してもらいました。
交流会の最後に、全体の前で、グループ毎でどのような話がされて、どのように感じたか、参考になったこと等、発表してもらいました。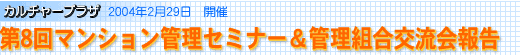
 セミナーでは、大阪弁護士会の金本弁護士に、住まい情報センターにも相談が多く寄せられている管理費等の滞納問題の対応策について、そして住宅金融公庫大阪支店まちづくり融資課の矢野課長に、皆さんの大切な資産であるマンションの維持管理に向けた公庫の支援について講演していただきました。
セミナーでは、大阪弁護士会の金本弁護士に、住まい情報センターにも相談が多く寄せられている管理費等の滞納問題の対応策について、そして住宅金融公庫大阪支店まちづくり融資課の矢野課長に、皆さんの大切な資産であるマンションの維持管理に向けた公庫の支援について講演していただきました。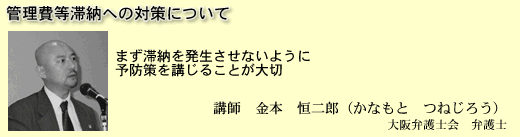
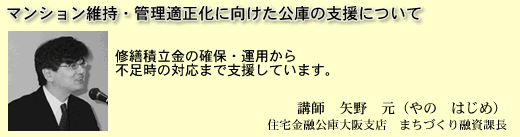
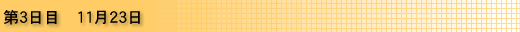
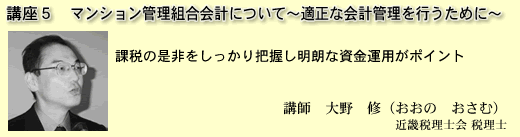
 法人登記をすることで社会的信用が増し
法人登記をすることで社会的信用が増し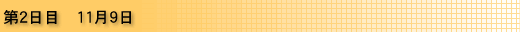
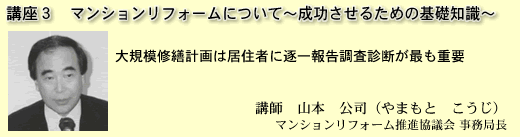
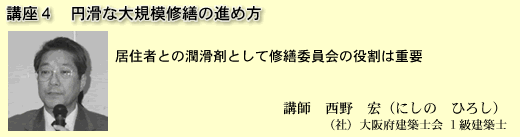 長期修繕計画は、管理組合の理事会や総会などで問題提起されて始まるのが一般的です。総会で長期修繕計画の実施の合意を得るのが一番目の問題点です。まず修繕委員会を設けます。理事会の役員が1年で交代するのに対し、修繕委員会の委員は2、3年のスパンで役をやるのが一番やりやすい方法だといわれています。
長期修繕計画は、管理組合の理事会や総会などで問題提起されて始まるのが一般的です。総会で長期修繕計画の実施の合意を得るのが一番目の問題点です。まず修繕委員会を設けます。理事会の役員が1年で交代するのに対し、修繕委員会の委員は2、3年のスパンで役をやるのが一番やりやすい方法だといわれています。 VDSL方式で手軽にブロードバンド化、マンション専用ホームページも活用できます
VDSL方式で手軽にブロードバンド化、マンション専用ホームページも活用できます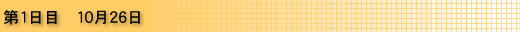
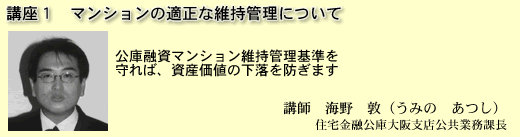
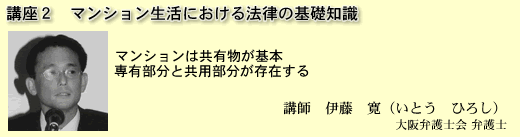

 いずれにしても大規模修繕は、皆さんの合意をもらってからも数年はかかるタイムスパンの長い事業です。ですからその間に、委員会を開いたら委員会の内容、理事会の内容などをこまめに皆さん方に公開していくことが大事です。後でクレーム等を出さないためにも、ぜひこれは実行してください。それと、建築士、弁護士、税理士その他さまざまな専門家をパートナーとして活用しながら、色々なシミュレーション、事例見学、資料の取り寄せを行ってください。
いずれにしても大規模修繕は、皆さんの合意をもらってからも数年はかかるタイムスパンの長い事業です。ですからその間に、委員会を開いたら委員会の内容、理事会の内容などをこまめに皆さん方に公開していくことが大事です。後でクレーム等を出さないためにも、ぜひこれは実行してください。それと、建築士、弁護士、税理士その他さまざまな専門家をパートナーとして活用しながら、色々なシミュレーション、事例見学、資料の取り寄せを行ってください。
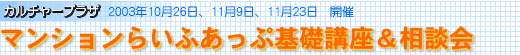
 今回の基礎講座では、新しく管理組合の役員になられた方などを対象として、マンション生活における法律の基礎知識、大規模修繕の進め方、管理組合会計など、適正な維持管理を進めていく上で必要となる基礎的な知識について、専門家がわかりやすく説明しました。計3日間にわたり合計9講座を開催し、3日目には総会の模様を実演し、問題点について専門家が解説する「模擬総会」を開催し参加者からも大変好評をいただきました。
今回の基礎講座では、新しく管理組合の役員になられた方などを対象として、マンション生活における法律の基礎知識、大規模修繕の進め方、管理組合会計など、適正な維持管理を進めていく上で必要となる基礎的な知識について、専門家がわかりやすく説明しました。計3日間にわたり合計9講座を開催し、3日目には総会の模様を実演し、問題点について専門家が解説する「模擬総会」を開催し参加者からも大変好評をいただきました。 ■久保井 聡明
■久保井 聡明 ■石原 健次
■石原 健次 ■岡本 森廣
■岡本 森廣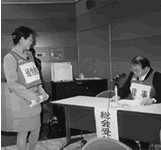
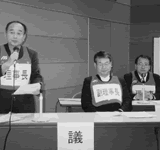
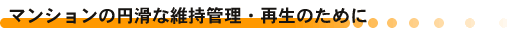
 生駒:やはり管理組合の皆さんに基本的な知識をまず知ってもらい、それから運営に関心を持っていただく、そのために広報でしっかり伝えていくことが重要でないかと思います。また管理会社や専門家をうまく活用していくことも重要です。住まい情報センターは、そのための必要な情報を入手でき、あるいは悩んだ時に相談できる場所として、また支援メニューの紹介・提供、いろんな専門家団体・事業者団体との繋ぎ役としての役割を果たせるよう頑張っています。 今後ともぜひ活用いただければと思っています。
生駒:やはり管理組合の皆さんに基本的な知識をまず知ってもらい、それから運営に関心を持っていただく、そのために広報でしっかり伝えていくことが重要でないかと思います。また管理会社や専門家をうまく活用していくことも重要です。住まい情報センターは、そのための必要な情報を入手でき、あるいは悩んだ時に相談できる場所として、また支援メニューの紹介・提供、いろんな専門家団体・事業者団体との繋ぎ役としての役割を果たせるよう頑張っています。 今後ともぜひ活用いただければと思っています。

 岡本:長期修繕して立派にしても耐震補強はどうにもなりません。私達の経験からしても30年代のマンションは、大きな地震には耐えられません。そうなると建替えを考えざるを得なくなりますが、人間はいろいろな考えを持っています。そういう時に一つの目的を共有しながら進める方法は、やはりPRだろうと思います。
岡本:長期修繕して立派にしても耐震補強はどうにもなりません。私達の経験からしても30年代のマンションは、大きな地震には耐えられません。そうなると建替えを考えざるを得なくなりますが、人間はいろいろな考えを持っています。そういう時に一つの目的を共有しながら進める方法は、やはりPRだろうと思います。

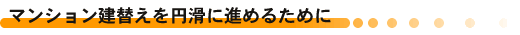
 元木:築年数の古いマンションがたくさん増えると何が問題かということですが、まずマンションという所有形態が1戸建てと決定的に違い、自分の所有物を自分で自由に処分できないという事です。共有物を処分する時は共有者全員の合意が必要です。修繕や建替えも民法では全員同意でないとできません。マンションという新しい居住形態ができた時に民法だけでは対応できないため、昭和37年に区分所有法ができ、昭和58年に大規模修繕や建替え決議について全員同意の部分が改正されました。
ここでようやく修繕や建替えというものを意識しはじめたということです。
元木:築年数の古いマンションがたくさん増えると何が問題かということですが、まずマンションという所有形態が1戸建てと決定的に違い、自分の所有物を自分で自由に処分できないという事です。共有物を処分する時は共有者全員の合意が必要です。修繕や建替えも民法では全員同意でないとできません。マンションという新しい居住形態ができた時に民法だけでは対応できないため、昭和37年に区分所有法ができ、昭和58年に大規模修繕や建替え決議について全員同意の部分が改正されました。
ここでようやく修繕や建替えというものを意識しはじめたということです。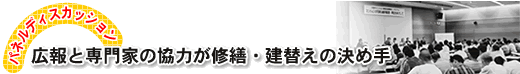
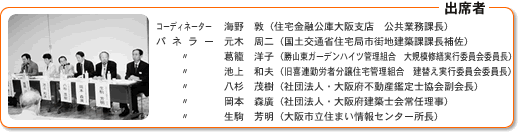
 海野:現在、築20年を超えるマンションは約60万戸といわれていますが、これが10年後には160万戸になり、国にとっても大変大きな問題です。そこで、マンションの維持管理を適正に行い、円滑に再生をするため、最近になってマンション管理適正化法・マンション建替え法が新しく制定され、区分所有法も大改正されました。今日は大規模修繕やマンション建替えの経験者をパネリストに迎え、マンションの維持管理・再生について、お話しいただきたいと思います。
海野:現在、築20年を超えるマンションは約60万戸といわれていますが、これが10年後には160万戸になり、国にとっても大変大きな問題です。そこで、マンションの維持管理を適正に行い、円滑に再生をするため、最近になってマンション管理適正化法・マンション建替え法が新しく制定され、区分所有法も大改正されました。今日は大規模修繕やマンション建替えの経験者をパネリストに迎え、マンションの維持管理・再生について、お話しいただきたいと思います。

 八杉:まずはマンション価格の現状をご認識いただきたいと思います。平成11年を100にすると、新築はマイナス7.6%落ち、中古は同22.1%落ちています。平均単価もそれにつれて下がっています。これはあくまでも平均値なので当然上下はあり、それがやはり管理の善し悪しになるかと思います。マンションの資産価値は、住み心地であって快適性の価値です。収益性のための維持管理であるビルと違い、分譲マンションは大規模修繕が近づいてくるまでは、まず外圧がありません。
そうすると維持管理の意識が希薄になりがちです。築15年以上経過しているマンションで、大規模修繕が行われず、長期修繕計画もないマンションは、いくら専有部分がリフォームされていても、近隣の類似マンションの半値以下になる場合もあります。これからのマンションは、維持管理の大競争時代に入っていくことになります。
八杉:まずはマンション価格の現状をご認識いただきたいと思います。平成11年を100にすると、新築はマイナス7.6%落ち、中古は同22.1%落ちています。平均単価もそれにつれて下がっています。これはあくまでも平均値なので当然上下はあり、それがやはり管理の善し悪しになるかと思います。マンションの資産価値は、住み心地であって快適性の価値です。収益性のための維持管理であるビルと違い、分譲マンションは大規模修繕が近づいてくるまでは、まず外圧がありません。
そうすると維持管理の意識が希薄になりがちです。築15年以上経過しているマンションで、大規模修繕が行われず、長期修繕計画もないマンションは、いくら専有部分がリフォームされていても、近隣の類似マンションの半値以下になる場合もあります。これからのマンションは、維持管理の大競争時代に入っていくことになります。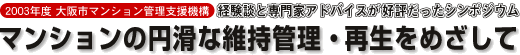
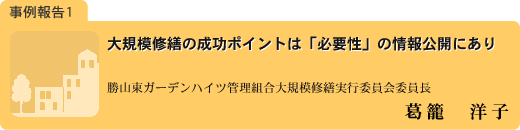
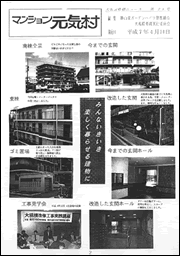 広報紙の効果もあり、平成4年にもう一度建物調査診断を行いました。その調査方法は、最初に設計監理者が調査診断の目的や手順などの説明をした後、全戸にアンケート調査を行い、管理組合の立ち会いで専門家が調査診断を行いました。それで傷み具合や適切な補修時期と補修概算額を写真付きの書類で提出していただきました。
広報紙の効果もあり、平成4年にもう一度建物調査診断を行いました。その調査方法は、最初に設計監理者が調査診断の目的や手順などの説明をした後、全戸にアンケート調査を行い、管理組合の立ち会いで専門家が調査診断を行いました。それで傷み具合や適切な補修時期と補修概算額を写真付きの書類で提出していただきました。